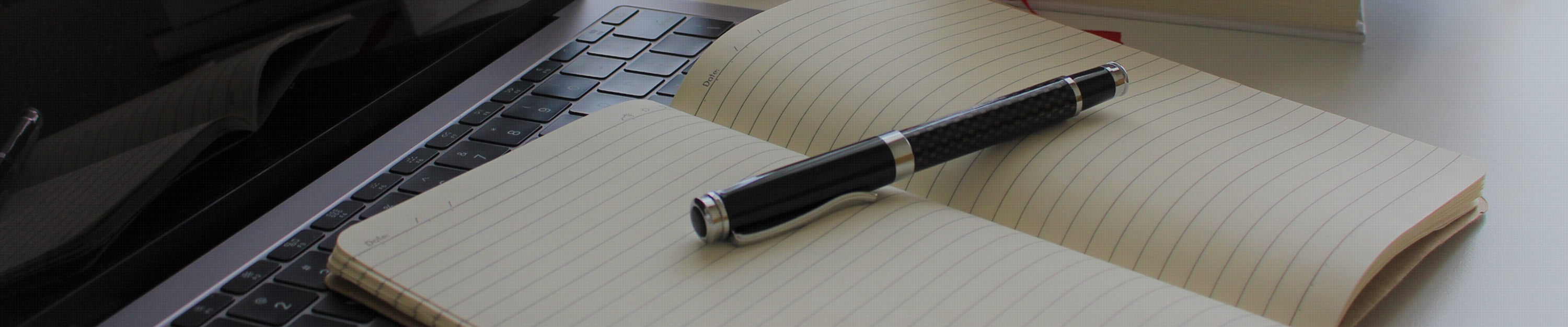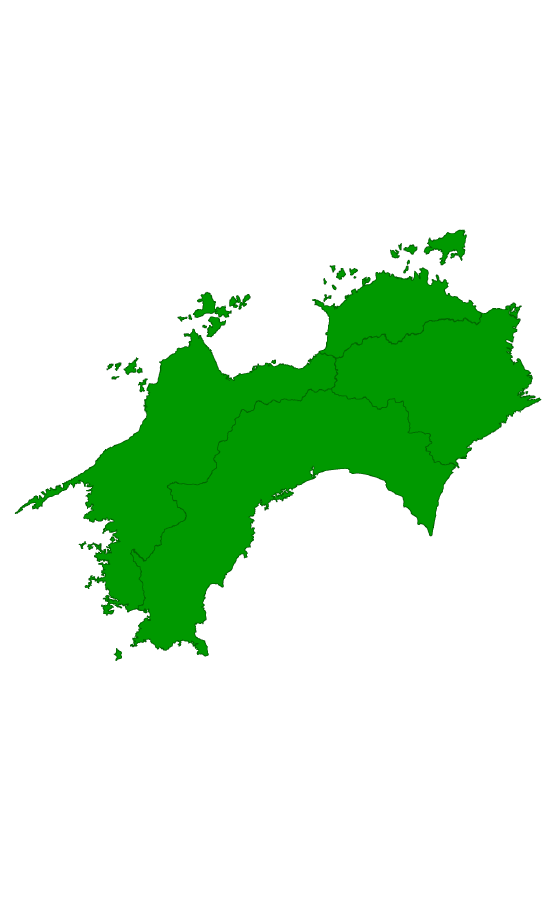工場製品加工室等の天井面防カビ対策

2025年11月12日
こんにちは。
工場倉庫建築設計ナビは地元愛媛県・香川県で工場や倉庫などの施設の新築や建て替え、改修、耐震補強等の設計業務を行っている建築設計事務所です。
今回は、温度管理の必要な工場天井面の防カビ対策についてご紹介いたします。
工場で発生する「天井面のカビ」の原因とは?
食品工場や精密製品加工場の作業場では、室温や湿度の管理が非常に重要です。衛生管理・製品加工精度等の観点から、一定の温度と湿度を保つ必要があるような場合、この管理がうまくいかないと「結露」によって天井面等にカビが発生することがあります。
今回の事例では、作業場の要求室温20℃に対し、夏場の天井裏温度が40℃近くに達し、この温度差によって天井面から伝わった冷気が天井裏の軽量鉄骨の表面を冷やして結露が発生。その水分が天井ボードに伝わり、カビの発生につながりました。
さらに、20℃の室温を排気する天井換気扇やダクト設備・冷媒配管や空調機表面についても、高温多湿になった天井裏の露点温度を下回ったことで結露が発生、これらも含め複合的な要因がカビ発生の原因となっていたのです。
実際の事例 ― 天井裏結露によるカビ発生の経緯
この工場では、当初26℃の室温設定で設計されていました。しかし、使用者側は「夏場の防カビ対策として室温を下げ除湿運転を続ける方がよい」と判断、節電とサーモオフを避けるために、除湿モードでの連続運転を続けていました。
結果的に、除湿運転が長時間続いたことで室温は20℃まで下がり、天井裏との温度差がさらに拡大。これにより結露が発し、却ってカビが発生しやすい環境を作ってしまったのです。加えて、長時間の除湿運転は電気代も上げてしまう結果となりました。
このように、意図せず「防カビ対策のつもりがカビを呼ぶ」ケースは少なくありません。温湿度のバランスを理解しないまま運転モードを固定することは、逆効果となる場合があります。
結露防止のために行った対策内容
当社ではまず、室内と天井裏の温湿度を測定し、露点温度を予測しました。露点温度とは、空気中の水蒸気が凝結し始める温度のことです。この数値をもとに、結露が発生しない適切な室温条件を検討しました。
そのうえで、空調機の機能を再確認し、サーモオフしない「除湿運転モード」から、適切に温度を制御できる「冷房運転モード」への切り替えを助言しました。これにより、不要な冷え過ぎを防ぎ、室内と天井裏の温度差を抑えることができました。
また、防カビ対策として空調機だけに頼らず、専用の除湿器を設置する方法も提案。室内の湿度管理を分散することで、安定した環境を保てるよう提案しました。
防カビ・結露対策のポイントまとめ
食品工場などの高衛生環境では、「温度を下げる=防カビ」とは限りません。
むしろ、設定温度が低すぎると結露が発生し、カビの原因となることもあります。
防カビや結露対策のポイントは以下の通りです。
・室温設定を根拠に基づいて行う(露点温度を考慮する)
・除湿運転モードを長時間続けない
・空調機と除湿器を併用し、湿度を適切にコントロールする
・温湿度データを定期的に測定し、環境変化を確認する
正しい知識と設備運用の理解があれば、カビの発生を防ぎながら清潔で安全な作業環境を維持することができます。
工場倉庫建築設計ナビは愛媛県、香川県を中心に四国全域で工場や倉庫の建築設計をサポートしています。
愛媛県、香川県など四国エリアで工場、倉庫の建築を検討されている方は、工場倉庫建築設計ナビにお任せください。